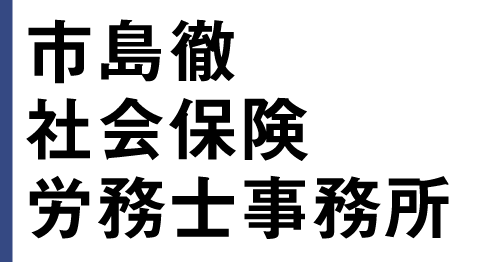以前の時間外居残り習慣も無駄ではなかったが…
改めて分かる組織力強化の業績獲得効果
◇◆◇ 個々の従業員強化より先に組織力強化を考えるべき時 ◇◆◇
たとえば、従業員の単なる居残り残業にも、他部門との情報交換や部下への指導などの意味があったと気付いた経営者がおられます。
しかし同時に、それを“残業時間”にダラダラと行わなければならなかったところに、『自社の組織マネジメントの深刻な問題を感じた』とも言われるのです。しかも、他にも同種の問題を多々発見したのだそうです。
それらはどんな問題だったのでしょうか。そして、そうした問題を“どのように”克服したのでしょう。そこで、その経営者の方の体験を事例としてまとめた“レポート”をご用意致しました。
ご希望の方には、標記の“レポート”を差し上げていますので、ご遠慮なく、お問い合わせください。