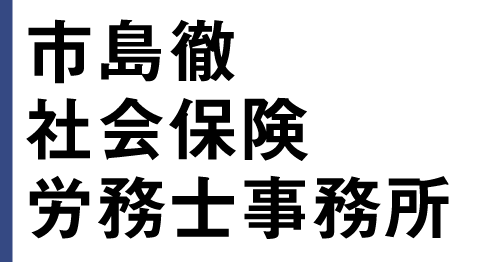デジタル化やDXという用語だけでの難易判定は危険システムに馴染みやすくする用語の意味理解
◇◆◇ 分かりにくいのはシステム用語が英語だからだった? ◇◆◇
たとえば、“アルゴリズム(algorithm)とは”から始まって、その内容を説明されるよりも、『(コンピューターの)“演算手順”を解説します』と言われてから詳細を聞いた方が、馴染みやすいでしょう。アルゴリズムは日本語では“演算手順”です。
そのため、システム用語がとっつきにくいのは、それが英語である上に、その用語を一旦日本語に訳してから解説する習慣が、ネット上にも書籍上にも乏しいからではないかと指摘する経営者もおられるのです。
そして、その経営者は、そんな奇抜なところから、デジタル化やDX等の用語に振り回されずに、効果的な学びや検討を進める事例を紹介するのです。
そこで、その“視点”の要点をまとめた《マネジメント・レポート》をご用意することと致しました。ご希望の方には、標記の“レポート”を差し上げていますので、お問い合わせページからお申し込みください。